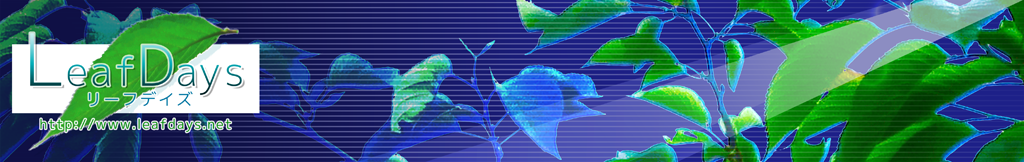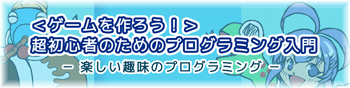|
どこで買う?
肥料は園芸店やホームセンターで購入できます。ネットでの購入も可能です。生ごみをリサイクルして肥料にすることも可能です。
どの肥料を買う?
肥料も土と同じように、植物に合わせていろいろな肥料を組み合わせて使うのがベストですが、これは素人には難しいです。植物に合わせた配合肥料がいろいろ販売されているので、最初はそれを使うようにしましょう。
ただし、上記、培養土を利用する場合、元から肥料などが配合された肥沃な土なので、最初は肥料は要りません。逆に肥料をやりすぎると栄養のやり過ぎによる障害を起こし、最悪枯れてしまう可能性があります。半年程度は肥料は不要です。(肥料が含まれていない場合もあります。袋に書いてある内容を読んで下さい。)
肥料の種類は大きく天然素材を使った「天然肥料」と化学合成した「化学肥料」に分けられます。
それぞれ使い分けがあり、
・「天然肥料」は効き目がゆっくりで穏やか。
・「化学肥料」は効き目が早く強い。
といった傾向になります。
「天然肥料」は多少多く与えても問題ありませんが、「化学肥料」の場合は強すぎて植物にダメージを与える可能性があります。場合によっては枯らしてしまうので注意しましょう。
基本は「天然肥料」を使い、即効性が必要な場合は「化学肥料」を使うことをお勧めします。
参考:当サイトのお勧めの肥料
収穫する植物には基本的に「天然肥料」しか使いません。
花など観賞期間を長くもたせる場合は栄養剤のような形の「化学肥料」を使う場合があります。
(基本的に化学肥料は使いません。)
当サイトのお勧めの肥料は「固形粒の配合醗酵油粕」です。
この肥料は菜種などの油粕に、大豆かすや骨粉などがバランスを考えて配合されており、多くの植物に対応できます。(胡蝶蘭などの水苔を使う植物など例外があります。)
粒状なので、植木鉢に植える場合などの取り扱いもしやすく、保存などの管理も楽です。
大きさは小粒、中粒、大粒などありますので植物や植木鉢の大きさに合わせて選んで下さい。
 
|
| アフィリエイト |
施肥の時期と間隔
施肥(せひ。肥料をあげること)の時期・間隔は、肥料の種類や与える植物によっても異なります。一ヶ月に一回という場合や数回という場合もあります。また、同じ植物でも人それぞれの経験により様々だったりもします。
施肥の時期には、
・元肥(もとごえ。植えつける時にやる肥料のこと)
・追肥(ついひ、またはおいごえ。植物の成長に合わせて随時やる肥料)
・寒肥(かんぴまたはかんごえ。春に向けて寒い時期に与える肥料。)
などのタイミングがあります。
初心者は「早く大きくなってほしい」、「栄養をつけてほしい」と、心配してついついあげてしまいます。
しかし、肥料はたくさんあげれば良いというものではありません。 多くあげることで逆に植物に被害を与え、最悪枯れてしまう場合もあります。
最初は「少ないかな?」ぐらいから始めた方が失敗しません。
園芸用の新しい培養土ではじめる場合、最初から十分な栄養が含まれていますので、半年は肥料をやらなくても問題ありません。(元からある土を使った場合は施肥して下さい。)
肥料が少ないからといって急に枯れるような事はありませんので、徐々に間隔を掴んでいきましょう。
【当サイトのお勧めの間隔】
・新しい培養土の場合:半年は肥料不要
・固形粒の醗酵油粕(有機配合肥料)の場合:3ヶ月に1回(3月、6月、9月、12月の3カ月毎)
植物の成長が著しい場合など、状態を見ながら回数を増減してみて下さい。
肥料の量
量は肥料の袋に書いてある分量を基本にして下さい。
一番だめなのは「あげ過ぎ」です。
心配で肥料をたくさんあげすぎるのは初心者が植物を枯らす大きな原因の一つです。
新しい土なら一年あげなくてもそれが原因で枯れるようなことはありません。(成長は悪くなりますが。)
最初は少ないぐらいの量からあげ始めて下さい。徐々に量を増やして適量を覚えましょう。
施肥の仕方
肥料によりあげ方は異なります。土に混ぜ込む場合や置肥(土の上に置いておく肥料)など、肥料の種類や用途に応じて変えます。
ここでの説明は、固形粒の醗酵油粕(有機配合肥料)を使った場合の説明をします。
施肥の仕方は、株から少し離して、植木鉢の淵に沿って小さな穴を掘り、固形粒を埋めていきます。固形粒は置肥としても使えますが、分解して栄養分になる過程でカビが生え、臭いが出ます。土に埋めてしまえば臭いはあまりしません。
(詳しい施肥の仕方は、肥料の袋を参照して下さい。)
保管の仕方
余った肥料は、袋の端を丸めてクリップで留めて、密封容器や密封袋に入れましょう。
そして、なるべく涼しい暗所に保管して下さい。
|